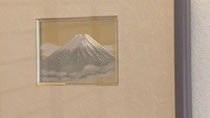- 私の地唄舞観
- ブログ
- 地唄舞
- 平家物語
- 渋沢栄一 ~趣味を持て~
- 山口周 新しい時代の資本主義
- スティーブン・R・コヴィー『役割と目標の特定』
- 中野善壽『ぜんぶ、すてれば』
- 踊独稽古 葛飾北斎
- 延期 第1回 叶和門下生の会
- 金子國義『舞妓』
- 富士松亀三郎『三味線の知識』
- よみがえる正倉院宝物
- 第1回花崎叶和門下生の会
- 鴨長明『方丈記』
- 斎藤幸平『人新世の資本論』
- 国立劇場評論『愚痴』
- 初舞の会『神明宮』at 阿佐ヶ谷
- 澁澤龍子『澁澤龍彦との日々』
- 第2回花崎叶和門下生の会 応挙館
- 郡司正勝『おどりの美学』新ばし金田中
- 盆踊り
- 今福龍太「言葉以前の哲学」戸井田道三論
- 舞い踊る文様~ルネ・ラリック
- 2024年1月8日神明宮at阿佐ヶ谷
- 鎌倉建長寺 得月楼「袖振る春風の会」
- 戸井田道三『きものの思想』毎日新聞社
- 建長寺 袖振る春風の会
- 建長寺 得月楼 袖振る春風の会
- 熱海 ウィーン少年合唱団
- 蒼梧記念館 浴衣会
- 沼津御用邸 栗名月の会
- 菊華荘 箱根富士屋ホテル
- 2025年1月初舞の会 阿佐谷神明宮
- 新年会 目白庭園
- 2025Qsガーデンイベント
- 箱根神社 奉納舞
- 相撲 千秋楽
- 岡本太郎
- お稽古の特色
- お教室のご案内
- 花崎叶和プロフィール
- お問い合わせ
- 地唄舞
- 平家物語
- 渋沢栄一 ~趣味を持て~
- 山口周 新しい時代の資本主義
- スティーブン・R・コヴィー『役割と目標の特定』
- 中野善壽『ぜんぶ、すてれば』
- 踊独稽古 葛飾北斎
- 延期 第1回 叶和門下生の会
- 金子國義『舞妓』
- 富士松亀三郎『三味線の知識』
- よみがえる正倉院宝物
- 第1回花崎叶和門下生の会
- 鴨長明『方丈記』
- 斎藤幸平『人新世の資本論』
- 国立劇場評論『愚痴』
- 初舞の会『神明宮』at 阿佐ヶ谷
- 澁澤龍子『澁澤龍彦との日々』
- 第2回花崎叶和門下生の会 応挙館
- 郡司正勝『おどりの美学』新ばし金田中
- 盆踊り
- 今福龍太「言葉以前の哲学」戸井田道三論
- 舞い踊る文様~ルネ・ラリック
- 2024年1月8日神明宮at阿佐ヶ谷
- 鎌倉建長寺 得月楼「袖振る春風の会」
- 戸井田道三『きものの思想』毎日新聞社
- 建長寺 袖振る春風の会
- 建長寺 得月楼 袖振る春風の会
- 熱海 ウィーン少年合唱団
- 蒼梧記念館 浴衣会
- 沼津御用邸 栗名月の会
- 菊華荘 箱根富士屋ホテル
- 2025年1月初舞の会 阿佐谷神明宮
- 新年会 目白庭園
- 2025Qsガーデンイベント
- 箱根神社 奉納舞
- 相撲 千秋楽
- 岡本太郎
2025Qsガーデンイベント · 13日 5月 2025
今年も世田谷区給田にございますQsガーデンのイベントに出演させていただきます。蒼梧記念館での座敷の舞になります。13時20分~ 、 14時20分~ の二部制になっております。弟子の頑張っている姿をぜひご覧いただきたく存じます。 日時 2025年5月17日㈯ 場所 東京都世田谷区給田 Qsガーデン内 蒼梧記念館 (第一生命創業者である矢野恒太氏旧宅)...
26日 3月 2025
白雲堆裏不見白雲 白雲堆裏に白雲を見ず、 流水声裏に流水を聞かず 白雲の真っ只中にあって白雲を見ることがなく、流水の潺が響く中にあって流水の声を聞くこともない。まっしぐらに走っているとき、余計なことをあれこれ考えたりすることもなく、ただひたすら、行動をしている。 さらには、その行動よりも先に人は判断しているらしい。...
26日 2月 2025
柳宗悦は、ウイリアムブレイクから大きな影響を受けている。そのひとつに「みえない実在」。 以前の師匠が、お稽古時によく言ったものだ。「見るな」と。...
新年会 目白庭園 · 20日 1月 2025
花崎叶和門下生の新年会を2025年1月19日㈪目白庭園で開催いたしました。例によって、希望者のみ、予定が合う人のみ参加の新年会でございます。今月は、たくさんの行事があったせいか(?)、午前中の開催ということでしょうか(?)寝坊により欠席という弟子がおりまして、思わず、笑ってしまいました。人生このくらいの塩梅がよろしいかと。身体が休みたいという、その心の声に忠実でございます。今年もゆるりゆるりといきましょう。このくらいが、ほんと、ちょうどよろしいのだと思います。頭で考えず、身体の声に忠実になりましょう。 目白庭園は、素敵でした。緑に囲まれ、池の中の鯉はぷくぷくとしており、何不自由なく優雅なお姿でごさいました。都心にこんな場所があるなんて。これも、地唄舞に出会い、弟子と知り合い、そんな御縁から、いただいた御縁でございます。 今年も、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
2025年1月初舞の会 阿佐谷神明宮 · 13日 1月 2025
今年度も阿佐谷神明宮にて初舞の会がございました。 今回は、弟子の数も増え、希望者を2つに分けて2日間参加させていただきました。 こちら阿佐谷神明宮の初舞が終わると、今年も始まった!という気がいたします。 風、光、木を感じながら、自然と一体となり、屋外の能舞台の上で舞うというのは、原点にかえります。...
菊華荘 箱根富士屋ホテル · 10日 12月 2024
2024年12月8日㈰ 富士屋ホテル 菊華荘にて門下生の会を開催いたしました。 強制参加は一切いたしませんので、希望者のみ。 松波千壽師匠と松浪千紫先生に地方をお願いいたしました。 舞も、もちろんそうですが、三味線も人がそのまま映し出されます。 松波千壽師匠と松波千紫先生の音とお唄。感無量です。...